 |
1923亥年 3月 26日 - 1945酉年 3月 24日 時代の風に逆らいきれず、陸軍伍長として那覇へ向かう途上海に沈む。 銃口を人民に向けず世を去ったことは、一つの救いと言えるかも知れない。 |
 |
1923亥年 3月 26日 - 1945酉年 3月 24日 時代の風に逆らいきれず、陸軍伍長として那覇へ向かう途上海に沈む。 銃口を人民に向けず世を去ったことは、一つの救いと言えるかも知れない。 |
| ★【論壇】 03/05/27沖縄タイムス |
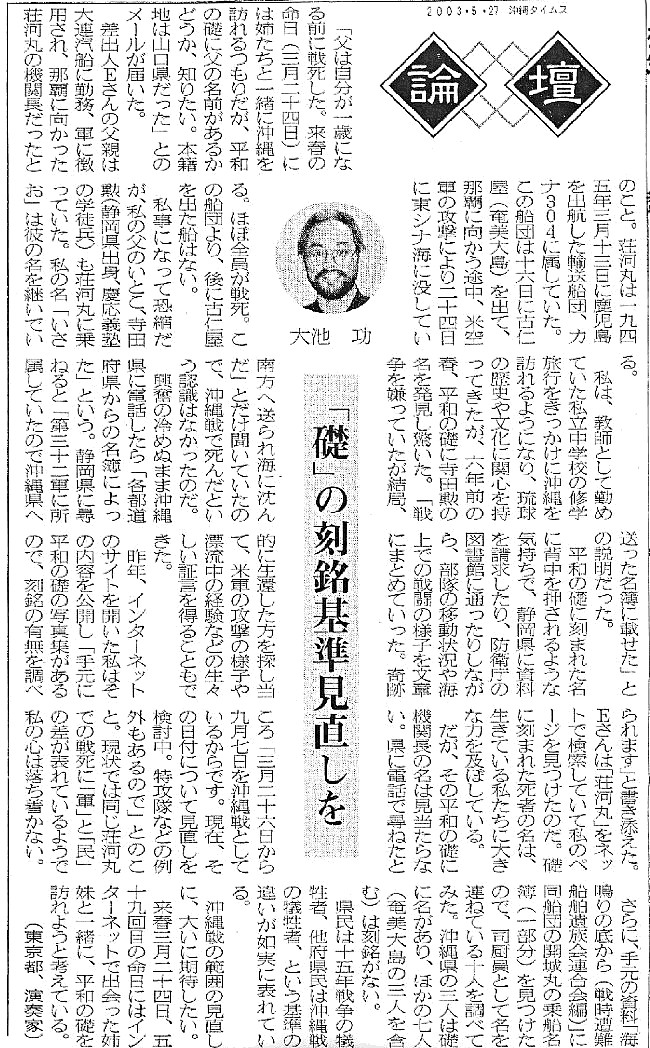 |
「父は自分が一歳になる前に戦死した。来春の命日(3月24日)には姉達と一緒に沖縄を訪れるつもりだが、平和の礎に父の名前があるかどうか、知りたい。本籍地は山口県だった」との【*1】メールが届いた。 【*2】差出人Eさんの父親は大連汽船に勤務、軍に徴用され那覇に向かった荘河丸の機関長だったとのこと。【*3】荘河丸は1945年3月13日に鹿児島を出航した輸送船団、カナ304に属していた。この船団は16日に古仁屋(奄美大島)を出て那覇に向かう途中、米空軍の攻撃により24日に東シナ海に没している。ほぼ全員が戦死。この船団よりあとに古仁屋を出た船はない【*4】。 私事になって恐縮だが、私の父のいとこ【*5】、寺田勲(静岡県出身、慶應義塾の学徒兵)も荘河丸に乗っていた。私の名「いさお」は彼の名を継いでいる。 私は、教師として勤めていた私立中学校の修学旅行をきっかけに沖縄を訪れるようになり、琉球の歴史や文化に関心を持ってきたが、6年前の春、平和の礎に寺田勲の名を発見し驚いた。「戦争を嫌っていたが結局、【*6】南方へ送られ海に沈んだ」とだけ聞いていたので、沖縄戦で死んだという認識はなかったのだ。 【*7】興奮の冷めぬまま沖縄県に電話したら「各都道府県からの名簿によった」という【*8】。静岡県に尋ねると「第32軍に所属していたので沖縄県へ送った名簿に載せた」という説明だった。 平和の礎に刻まれた名に背中を押されるような気持ちで、静岡県に資料を請求したり、【*9】防衛庁の図書館に通ったりしながら、部隊の移動情況や海上での戦闘の様子を文章にまとめていった。奇跡的に生還した方を探し当て、米軍の攻撃の様子や漂流中の経験などの生々しい証言を得ることもできた。 昨年インターネットのサイトを開いた私はその内容を公開し【*10】「手元に平和の礎の写真集があるので、刻銘の有無を調べられます」と書き添えた。Eさんは「荘河丸」をネットで検索していて私のページを見つけたのだ。【*11】礎に刻まれた死者の名は、生きている私達に大きな力を及ぼしている。 だが、その平和の礎に機関長の名は見当たらない。県に電話で尋ねたところ「3月26日から9月7日を沖縄戦としているからです。現在その日付について見直しを検討中。特攻隊などの例外もあるので」とのこと。現状では同じ荘河丸での戦死に「軍」と「民」の差が表れているようで私の心は落ち着かない。 さらに、手元の資料「海鳴りの底から(戦時遭難船舶遺族会連合会編)」に同船団の開城丸の乗船名簿(一部分)を見つけたので、司厨員として名を連ねている10人を調べてみた。沖縄県の3人は礎に名があり、他の7人(奄美大島の3人を含む)は刻銘が無い。 県民は15年戦争の犠牲者、他府県民は沖縄戦の犠牲者、という基準の違いが如実に表れている。 沖縄戦の範囲の見直しに、大いに期待したい。 来春3月24日、59回目の命日にはインターネットで出会った姉妹と一緒に、平和の礎を訪れようと考えている。 (東京都、演奏家) 【大池の注(03/05/30に記録)】 *1 原文「と言う」 *2 原文、改行しない *3 原文では「。」ではなく「……」で、改行 *4 原文では「無い」 *5 原文では「従兄」 *6 原文では「、結局」 *7 原文では改行しない *8 原文では「言う」 *9 原文では読点がない *10 原文では「、」がはいる *11 原文では改行 【投稿時(03/05/22)に付記したルビの要望、その他のメモ】 荘河丸=そうがまる 古仁屋=こにや 司厨=しちゅう 開城丸=かいじょうまる 11字×109行=1199字 |

  |
