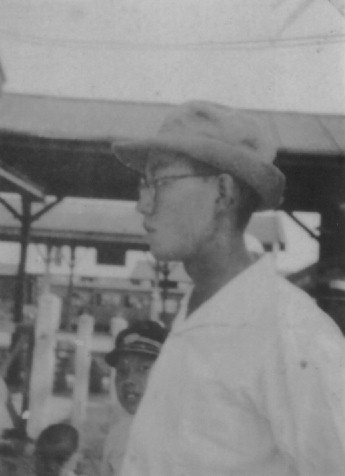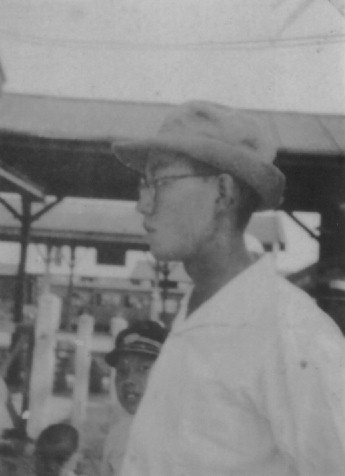■海からやってくるものは…… (イサヲの旅立ち・その3)
ぼくの好きなうた(連載第13回) ラフティ いさを
<前号までのあらすじ>
1944年冬。浜松にすむヒサヱ(数え17歳)は微熱でまどろんでいた。中部129連隊から、久しぶりに外出してきた兄イサヲ(22歳)は沖縄行きの命令を受けていたが、多くは語らず、ラバウル小唄の替え歌を繰り返し唄って聞かせるだけだった。
「さらばひーちゃんよ、また来るまではしばし別れの涙が滲む」
数日後、イサヲは疾走する軍用列車で鹿児島へ。そして制海権のない海路を沖縄へ向けて輸送船団は進む。何とか無事に奄美大島の古仁屋港まではたどり着いたが、那覇に向かううちに魚雷攻撃を受け船団中の一隻を失う。米空母15隻と米艦載機延べ940機による「九州沖航空戦」の日のことであった。
一時、泗礁山錨地に避難した8隻は3月22日再び那覇に向けて航行を始めた。留まるのも危険、戻るのも危険、という最悪の状況、一か八か那覇を目指したのだ。
連合国軍の18万余の兵士も、すでにウルシー環礁経由で沖縄近海に配備されていた。
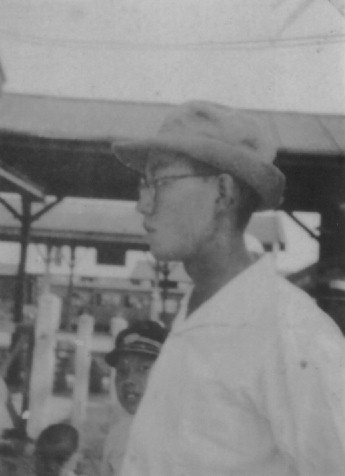
袋井駅 にて イサヲ18歳 (顔が見えているのが従弟13歳) '40年 8月
干戈交ゆる 幾星霜
七度重なる 感状の
いさをの陰に 涙あり
ああ今は亡き 武者の
笑って散った その心
(加藤部隊歌-隼戦斗隊 作詞 田中林平)
敗走にも等しい、虚しい航行を続ける荘河丸の上でイサヲは思った。
何という皮肉。この数年間に、自分の名が「いさを」であることを恨んだ数々の瞬間を思い出していた。
商学部の学生でありながら召集され、戦場からは最も遠くにいたい、という願いが絶たれた瞬間…
水戸にある陸軍の通信学校に通うことで、少しでも前線から遠ざかりたいという思いが叶った瞬間…
幹部候補生としての昇級を断ることで自分の意思を確認した瞬間…
部隊からの外出時に自宅でぐずぐずしていたときは、従兄弟が機転を利かせて消防自動車を呼びつけ無理矢理送られたおかげで営倉は免れた…
第32軍に転属とわかり、母親代わりの叔母に泣きついたこと、妹に「さらば、ひーちゃんよ…」と歌ったこと…全てが遠い昔のようにも思える。
手柄を立てた証=イサヲ(勲)、とは何度考えても皮肉な名。自分ほど戦を嫌った者が、こんな無力な徴用船で前線に補充されていく。戦う、とは一体何なのか。
3月23日、連合国軍艦隊は沖縄への攻撃を始める。午前8時、艦載機グラマンが小禄飛行場(現、那覇空港)と那覇港を攻撃。疎開船への乗船準備をしていた数千人は防空壕へ走る。実質的に沖縄戦が始まったのだ。が、日本軍は、3月18〜20日の九州沖海戦で被害を受けた米艦隊がウルシー環礁に避難する途中の腹いせ的攻撃に過ぎない、と高をくくっていた。三日間のうちに敵の空母5隻他を撃沈・大破した、という誤報に大本営が踊らされていたのだ。態勢を立て直して沖縄に敵が侵攻するのは二か月後と判断していたという。実際には戦列から脱落したのは空母フランクリン一隻だけだったのだ。
米機動部隊は空母10隻を中心にすでに海上で補給を受けて態勢を整え終えていて、3月24日午前には、沖縄島南部沖合いから艦砲射撃を始める。これは慶良間上陸(3月26日)の陽動作戦に過ぎないものであった……
では、でいご娘の皆さんに唄ってもらいましょう。
若さる時ね 戦の世
若さる花ん 咲ちゆーさん
家ん元祖ん 親兄弟ん
艦砲射撃ぬ 的になてぃ
着る物 喰ぇ物 むる無らん
スーティチャーかでぃ 暮らちゃんや
うんじゅん わんにん
ぃやーん わんにん
艦砲の喰ぇーぬくさー
(比嘉恒敏 「艦砲の喰ぇーぬくさー」第一節)
沖縄島の地形さえ変えてしまったという艦砲射撃の「喰い残し」なのだという自己認識。戦後間もなく流行った言い方だという。
比嘉恒敏は読谷山楚辺の出身。
米軍が沖縄上陸地点の読谷山--北谷に浴びせた艦砲について、後にニミッツ(当時の米海軍元帥)はこう書いた。
4月1日朝、太平洋のどの海岸にも加えられたことのないような猛烈きわまる艦砲射撃を……
その日だけで艦砲は45000発、他にロケット砲などが55000発以上という記録が残っている。
比嘉恒敏は戦局の悪化してきた頃には、大阪に単身で出稼ぎをしていて沖縄戦を直接は経験しなかったのだ。が、前年の夏に息子と両親を疎開船対馬丸(44年夏魚雷で撃沈された)で失っており。さらにその後大阪に呼び寄せた妻と大阪で生まれたもう一人の息子を空襲で亡くしている。
忘る勿かれ----この人々の名も摩文仁の「平和の礎」に刻まれてある。
私ラフティは読谷山楚辺の近くにあるチビチリガマではときどき一人歌っています。
我親喰ぁたる あぬ戦
我島喰ぁたる あぬ艦砲
生まり変わてぃん 忘らりゆみ
誰があぬ様 しいんじゃちゃら
恨でぃん 悔やでぃん 飽きじゃらん
子孫末代 遺言さな
(「艦砲の喰ぇーぬくさー」最終節)
誰が哀れを強制したか、この問は事ある毎に繰り返されなくてはなるまい。たとえ生まれ変わっても、と唄った比嘉恒敏は73年に交通事故で亡くなる。
歌が歌われる限り「遺言」は語り継がれるに違いない。
幾つもの痛みを背負わされても
島唄の響きは絶えることはない
鉄の嵐が島に吹き荒れても
榕樹の根は大地にますます広がる
幾世いちまでぃん 風吹ちゅるままに
流れ行くままの白雲の如に たおやかな白い雲のように
(「流れ行く白雲の如に」なーぐしく よしみつ)
荘河丸、船上のイサヲ伍長のその後や如何に。次回はいよいよ「イサヲの旅立ち―最終回」です。

【お知らせ】
「平和の礎」の全てを写真撮影し出版した「写真記録平和の礎(日本・米国・台湾・朝鮮民主主義人民共和国・大韓民国)沖縄全戦没者刻銘碑」(95年那覇出版社・約4kg)を私自宅に持っております。沖縄戦戦没者(とおぼしき方)の氏名と本籍地(沖縄県以外の場合は都道府県まで)をお知らせ下されば刻銘の有無を確かめられます。ラフティまでご連絡を。
参考資料
チバリヨーウチナー(CD CCD760 97年音楽センター 寿ほか)
軍歌大全集(CD VICL-5306 95年 ビクターエンタテインメント)
改訂版沖縄戦(大城将保 88年 高文研)
太平洋海戦史(ニミッツ、ポッター 92年恒文社)
沖縄作戦の統帥(大田嘉弘 84年相模書房)
戦時船舶史(駒宮真七郎 91年)
戦時輸送船団史(駒宮真七郎 87年)
太平洋戦争沈没艦船大鑑
海鳴りの底から(戦時遭難船舶遺族会連合会 87年)
帝国陸軍の最後(伊藤正徳 61年)
新沖縄ワールド(沖縄タイムス94・10・16記事)
ルビ
滲 にじ
疾走 しっそう
古仁屋 こにや
艦載機 かんさいき
八 ばち
干戈 かんか
幾星霜 いくせいそう
感状 かんじょう
亡 な
武者 もののふ
隼戦斗隊 はやぶさせんとうたい
虚 むな
荘河丸 そうがまる
召集 しょうしゅう
水戸 みと
叶 かな
従兄弟 いとこ
無理矢理 むりやり
営倉 えいそう
免 まぬか
叔母 おば
証 あかし
徴用船 ちょうようせん
小禄 うるく
疎開 そかい
防空壕 ぼうくうごう
多寡 たか
撃沈・大破 げきちん たいは
大本営 だいほんえい
艦砲射撃 かんぽうしゃげき
慶良間 きらま
陽動 ようどう
若 わか
時 とち
戦の世 いくさ ゆ
家 やー
元祖 ぐわんす
親兄弟 うゆあちょーでー
艦砲射撃 かんぽうしゃげき
着 ち
物 むん
喰 く
物 むん
無 ねー
流行 はや
読谷山楚辺 ゆんたんざそべ
読谷山 ゆんたんざ
北谷 ちゃたん
元帥 げんすい
対馬丸 つしままる
撃沈 げきちん
勿 な
摩文仁 まぶに
礎 いしじ
我親喰 わーうやく
戦 いくさ
我島喰 わーしまく
誰 たー
様 じゃま
強 し
恨 うら
悔 くや
飽 あ
子孫末代 しすんまちでー
遺言 いぐん
伍長 ごちょう
船倉 せんそう
被弾沈没 ひだんちんぼつ
荘河丸 そうがまる
【イサヲの旅立ち】の続きを見るにはここをクリック
[BBS] へ行く
00
表紙のページに戻る
 |
← 感じたこと 考えたこと お伝え下さい |